令和7年6月
6月30日中学年水泳学習
学校支援アドバイザーの先生をお迎えして、中学年が水泳学習を行いました。泳ぐのが得意なグループに、背泳ぎや平泳ぎを教えてくださいました。
「腕を伸ばして、こう回す。」教わりながら児童も一緒に動いてみます。陸の上での動きを水の中で同じようにやるのは難しいですが、何回か繰り返すうちに、だんだん形になってきました。
初めて平泳ぎをやった児童に感想を聞くと「腕、足、のびる、の、のびるが楽しかったです。」と教えてくれました。大満足の時間となりました。ご指導ありがとうございました。



6月27日「人権を考える」
人権擁護委員の方をお招きして、4年生が人権教室を行いました。いじめのビデオを見た後、自分がいじめにあったらどうするか、いじめを見たらどうするかを一人一人、そしてグループで考えました。
いじめにあったら、先生や親に相談するという考えがとても多かったです。我々教員を頼りにしてくれることは嬉しいことです。いじめを見たらどうするかも、やはり相談するという考えが多かったです。人権は、安心、自信、自由が大切であること、いじめにあったら「いやだ」と伝える、逃げる、相談するということが大切であることを改めて教わりました。
「いじめが起きたら、その時どうすればよいかをよく考えました。」「自分が知らぬ間に人を傷つける言葉を言っていないかと、今までを振り返ったり確かめたりする時間ができました。」「友達の気持ちを考えて生活すると決めました。」など、いじめについてしっかり考えた感想が書かれていました。皆で、心あったかな桜台小にしていきましょう。



6月26日「浮いて待て講習」
消防署の方をお招きして、中、高学年が「浮いて待て講習」を行いました。以前は「着衣泳」と言っていましたが、今は泳がず力を温存して浮いて待つことが推奨されています。
浮く物は身近にたくさんあります。靴、ランドセル、クーラーボックス、未開封の袋菓子、ペットボトルなど、実際に沈めた後浮いてくる様子を確認することができました。また、浮いている間に声を出し続けると肺の空気が少なくなってしまうので声を出さないこと、誰かが流されても自分で助けに行かずに浮く物を投げること、大人を呼ぶことなどを教わりました。
ペットボトルを使って浮く際は、蓋を下に向けて、おへそのあたりで抱えて静かに浮きます。ラッコのように顔をしっかり上げると、息を吸うことができます。それを教わると、すっかり上手に浮くことができるようになりました。流れるプールを作って、流れの中でも浮く練習もできました。両脇に浮く物を挟んで、ペンギンのように浮くこともできることが分かりました。経験は大切です。
今日は本年度初めての「気軽な授業参加」の時間でもありました。保護者の方10名も一緒に参加してくださいました。「指導を見て、ためになりました。」「見学できて楽しかったです。」「万が一水難事故に会ったとき、思い出してほしいです。」などの感想が聞かれ、有意義な時間となりました。濡れた着衣を絞るのも手伝ってくださいました。ありがとうございました。他の保護者の皆様も、ご家庭でどんなことを学んだのか話題にしてみてください。






6月25日「桜台小、幸せゆったり時間」
水曜日の昼休みは35分間のロング昼休みです。時折激しい雨が降って外での活動はできませんでしたが、室内で、なんとも穏やかな時間が流れていました。
友達とオセロやカードゲーム、折り紙、粘土を楽しむ子、図書室で本を借りる子、学級でレクを計画して行っているクラス、担任を囲んで大盛り上がりのゲームをしているグループ、映像に見入っている子、どの児童も自由で温かな時間を楽しんでいました。時にはこんな幸せ、ゆったり時間もいいですね。
今朝の通学時間帯は、一時、ものすごい雨が降っていました。靴の児童はもう靴下までびしょびしょでした。ランドセルに替えの靴下を1足入れておいていただくと、急な雨が降ってきたときも履き替えて気持ちよく1日を過ごすことができます。高学年でも同様です。ぜひ、よろしくお願いします。



6月24日「自分たちが出したごみの行方」
4年生が社会科見学で、印西クリーンセンターの見学に出かけました。ちょうど燃やすごみの回収日だったので、ゴミ収集車が次々と入ってくる様子を見ることができました。ゴミクレーンでゴミを持ち上げては放すことを繰り返して燃えやすくする様子も、係の方のご配慮で間近で見ることができました。
年末、ゴミに混ざっていたリチウムイオン電池が原因で火災が起こったことも知りました。また、クリーンセンターに回収されるゴミの中には、資源物も多く含まれていることも知りました。ゴミの出し方にも気をつけたいという声が聞かれました。
自分たちが何気なく出したゴミの行方を知ることで、今後の意識も変わってくることを願います。ご家庭でも話題にしてみてください。



6月23日「白井市の自慢」を伝えよう
5年生の国語の学習で、伝わるように構成を考えて「町じまん」を発表する学習があります。皆が白井市の魅力について調べ、同じテーマの仲間と話し合いながらまとめていました。
白井市と言えばやはり、梨。梨について発表しようと考えている児童が多かったです。その他にもプラネタリウム、お寿司屋さん、パン屋さん、身近な虫など思い思いの町じまんがありました。その中で3月に桜台センターで行われる「さくせんフェスタ」を挙げている児童がいました。
「さくせんフェスタ」は桜台センターの行事ではありますが、地域の方々が大勢集まる催しで、児童が企画・運営するコーナーもある桜台の一大イベントです。それを「自慢」とすることに大きな喜びを感じます。自分たちで桜台を盛り上げていくという思いを感じました。将来出身地を聞かれたら「千葉県白井市桜台です!」と胸を張って言ってくれる児童を育てていきたいです。



6月20日「外国からの友達」
今週1週間、4年生に体験入学に来た友達がいました。普段はグアムで学んでいる児童です。1週間一緒に勉強し、一緒にプールに入り、一緒に遊んで過ごしました。今日はそのお別れの日です。「楽しかった。」と慣れない日本語で感想を伝えてくれました。
一緒に来てくださった保護者の方は、日本の教育の素晴らしさを感じたとお話しくださいました。社会科のクリーンセンターの見学とからめて、国語で意見文の学習をし、そのための漢字も習い、様々な学習が関連付けられていることに驚いていらっしゃいました。また、まだ紙文化が残っていて、実際に自分で字を書くというのも大切だと感じられたようです。母国では、紙に書く習慣はもうないそうです。どちらが良いのかは分かりませんが、いい体験だったことは確かです。
皆で作ったレイをプレゼントして、別れを惜しみました。1週間もいると、すっかり仲間になり、離れがたくなっています。昇降口でも、大勢が輪を作って話していました。子どもに国境はありません。



6月19日「いかのおすし」
1年生がALSOK安全教室を行いました。「いかのおすし」は、もう1年生でも知っている有名な防犯の合い言葉です。ついていかない、乗らない、大声で叫ぶ、すぐ逃げる、知らせるを一つ一つ確認していく学習でした。
両手を広げてみると、大人と子どもの腕の長さは倍ぐらいあります。大丈夫と思って近づいても、あっという間に腕を捕まれてしまいます。そうならないために、車なら後方に、大きな声で「助けて!」と言いながら逃げる練習もしました。最後に、不審者役の方から声をかけられた後、安全なところで大人(担任)にその様子を話すことも練習しました。
桜台小の若葉の会の方たちが見守りワッペンを配布してくださっています。お買い物や犬の散歩の時など、黄色のカードを身に付けて歩いてくださるだけで、それは大きな抑止力になります。地域全体で、子どもたちの安全を守ってください。そして、「挨拶ができる街は犯罪が少ない街」です。ぜひ挨拶も盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。



6月18日「6年校外学習」
6年生が校外学習に行ってきました!場所は国会と科学技術館!
国会はでは、「テレビや教科書で見た場所だ!」という言葉も聞かれました。社会科で政治について学習していますが、本物に触れることでさらに理解が定着したと思います。
科学技術館では、体験を通して科学に触れることができました。科学で起こる不思議な体験をわかりやすく体験しながら学ぶことができ、グループで楽しみながら活動していました。






6月17日「低学年も水泳指導スタート」
高学年、中学年に続き、本日低学年の水泳指導がスタートしました。1年生は初めての学校のプールです。2年生をお手本に、水泳指導のルールを理解して安全に水に親しむことができました。
午後の高学年の水泳指導の初めの一幕紹介。水慣れのために座ってバタ足をした時のこと。「では、かけ算九九の7の段を言いながらバタ足をしましよう。」という教師の言葉で始まったバタ足。いつまでも続いているので一度ストップ。「分からなくなっちゃったかな。」と聞くと正直に「はい。」という返事。きっと九九に集中したら言えているはずですが、そこに慣れないバタ足と顔に飛ぶ水しぶきで混乱したようです。正直で一生懸命な一面が垣間見られた、かわいい一幕でした。がんばったね。



6月17日「材料の特性を生かして」
6年生が、図画工作科の「木と金属でチャレンジ」の学習で、木や金属の特性を生かしながら設計図を基に作品作りに取り組んでいます。設計図を見せてもらうと、様々なアイデアがあふれていました。曲線もあり、それをどう表現するのか、材料の特性や使う道具を考えながら進めます。
糸のこを上手に使いこなしているので聞いたら「5年生の時に使ったから、慣れています。」と自信満々で教えてくれました。その言葉どおり、安全に気をつけながら、曲線も上手に切り出しています。ペンチで針金を丸めながら、花を作っている児童もいました。他にもキリやのこぎり、カッターなども用意されています。
「これは、筆を乾かす台にします。」と枝を立てている児童が教えてくれました。出来上がったら、実生活にも生かせそうです。



6月16日「水泳学習始まる」
先週の月曜日に高学年、そして本日、中学年がプール開きを行いました。朝から暑い日だったので、朝から水泳の時間を心待ちにしていたようです。
まずは水慣れをして、皆で同じ方向に回る「流れるプール」、そして一斉に力を合わせる「波」を行いました。久しぶりの水に気持ちよく体を伸ばしたり、波の力でプカプカ浮かぶ感覚を楽しんだりしました。その後、泳力を調べて、次回の練習グループを作りました。「楽しかったあ。」とニコニコで帰ってきました。
水に入る経験は貴重です。命を守る学習にもなります。気を引き締めながら、水に親しんでいきます。



6月13日「未来の先生」
大学生が、教員の勉強のために週1回学校を訪れ、各学年を回っています。今日は1年生と一緒に一日を過ごしました。
担任のアドバイスを近くで聞いて、実際に自分でもできるように子どもたちの間を回っていました。給食も、児童と一緒。休み時間は、けがをした3年生を保健室まで連れて行ってくれました。
子どもたちの下校を見送った後感想を聞くと「いやあ。元気ですね。」と一言。今日は、児童の気持ちが前向きになる担任の声かけが勉強になったと嬉しそうに教えてくれました。今年1年、全学年を回ると、子どもたちの成長段階も実感することでしょう。将来、どこかの学校で一緒に仕事ができるといいなと思っています。頑張れ!輝く未来の先生!!



6月12日「命を守る訓練」
学校に大人が侵入して暴れた事件が報道されたのは記憶に新しいところです。本校でも不審者対応訓練を毎年行っています。今回は、6年生教室に不審者が入った想定で行いました。
6年生は状況を見て、担任の指示をきっかけに、「行こう。」という互いの合図で、自分たちで避難することができました。他の教室も真剣に訓練に参加していました。全校で避難が終わった後、安全主任から、不審者から距離を取ること、反対に逃げること、悲鳴をあげないことという身の守り方を再度伝えました。
いつも近くに担任がいるとは限りません。自分の命は自分で守る。振り返りの時間にも各クラスでその言葉が聞かれました。お知らせしたとおり、昇降口や職員玄関は普段は施錠しています。少し不便ですが、ご協力をお願いします。



6月11日「にじいろ遊び」
今日のロング昼休みは、縦割り班ごとに集まって「にじいろ遊び」を行いました。「集まってえ。」6年生の声で1年生から6年生までが集まります。
ドッジボール、爆弾ゲーム、新聞紙タワー(新聞紙を工夫してどれだけ高く積めるか)、何でもバスケット(フルーツバスケットの自由課題版)、聖徳太子ゲーム(3人が一斉に言った言葉を当てる)、震源地はどこだ、いす取りゲーム、宝さがしなどで楽しみました。何でもバスケットでは、1年生が「赤白帽子をかぶっている人!」と言うと、6年生が「うまい!」と声をかけ、一斉に席を立って自分の椅子を探していました。どのグループからも盛り上がっている楽しそうな声が聞こえてきました。
「思ったより大変でした。」と終わってから6年生が教えてくれました。まだしっかり名前を覚えていなかったから、声をかけるのが難しかったそうです。これからも縦割り班活動は続きます。これからすっかり名前を覚えて、もっともっと仲良くなりそうです。



6月10日「雨過天晴」
「雨過天晴」(うかてんせい)という言葉をご存じですか。悪かった状態が良い方に向かう例えだそうです。なんだか、心まで晴れるようです。今日6年生から教わりました。国語科の学習で、雨に関連する言葉探しをしていました。
「霧雨」はシャワーみたい、「小雨」はつぶつぶ。肌に触れる感覚で説明していました。今日の九州地方は「しのつく雨」(篠竹を束ねた物が落ちてくるように、細い物が密に激しく飛んでくる、つまり雨が激しく降るさま)でしょうか。被害が大きくならないことを祈ります。
初めて出会う言葉に、「へええ。」と関心したり、読み方が分からず四苦八苦したりしながら学習が進んでいました。新しいことを知ることは楽しいことです。言葉を豊かにして、表現できることを増やしていきたいものです。
関東地方が梅雨入りしました。



6月9日「みんなで子どもたちを育てる」
コミュニティー・スクールが2年目を迎えました。本年度初めての学校運営協議会(コミュニティー・スクールの内容について話し合う場)を行いました。委員9名の他に、4名も地域の方が参加してくださいました。
今年は、子どもたちの「挨拶」「コミュニケーション力」を育てることを目標に、本年度の活動計画や組織の分担、コミュニティー・スクールの概念の周知方法などについて話し合いました。まあ、皆さんのアイデアの豊富なこと。地域の皆さんも巻き込んで、様々なご意見をいただきました。ありがたいことです。
「みんなで子どもたちを育てる」そんなお気持ちがあふれていました。保護者の皆さん、こんなにも子どもたちは地域の方から大切にされています。今年のスペシャルスタディーも昨年度同様、児童・保護者・地域の方の3世代交流を目指して楽しく開催する予定です。地域の方と行うパトウォークも、桜台の安全を守る大切な取り組みです。ちょっと頭の片隅にいれておいてください。


6月9日「邦楽体験教室」
第3部会(印西・白井)で二十数年前から行われている「邦楽体験教室」が今年も開催されました。日本の伝統的な楽器「箏(こと)」を、本校では4年生が体験します。
講師の先生をお迎えし、「さくらさくら」の弾き方を教えていただきました。右手の親指に箏用の爪をつけ、箏用の楽譜を見ながら「七、七、八~♪」と演奏します。はじめは小さく弱々しかった音色が、練習を重ねるにつれ自信をもった大きい音になってきます。最後には「かーらりん」という奏法も教えていただき、みんなで合奏を楽しみました。
なかなか触れることのない「箏」の演奏体験ができるとても貴重な機会でした。これをきっかけに和楽器への興味が広がると嬉しく思います。



6月6日「5人の力」
先日の3部会陸上大会の記録をもって、郡の陸上大会に臨んだ6年生男子リレーチーム。朝のスコールのような雨の影響で(競技場のある成田は、朝開会式前にものすごい雨が降ったそうです。)決勝はなく、タイムレースで順位が決まりました。
一発勝負です。心を一つにレースに臨みました。その結果、5人の力を集結し、4位入賞を果たしました!素晴らしい走りを見せてくれました。結果を校内放送で流すと、歓声が起こっていました。
この経験は、きっと将来どこかで自信となって、自分を支えてくれることでしょう。おめでとう!



6月6日「のびのび」
フラワーガーデンサークルの皆さんが、暑い中、昼過ぎまで、夏用の花壇を作成してくださいました。今までの花を整理して、新しい花を形よくおしゃれに植えてくださいました。ありがたいことです。
今回のテーマは何ですかと聞くと「テーマはのびのびです。」との答え。思ったよりお花の数が少なかったようで、間隔を広めに取ったとのことでした。「広い間隔で、のびのびと!」と笑いながら教えてくださいました。
何でも余裕は大切です。人も花ものびのびと!



6月6日「窓辺の光景」
1年生教室に行くと「見て見て!ぼくの魚。」と手を引かれました。行ってみると、窓に素敵な図工の作品が貼られていました。「ひかりのくにのなかまたち」の学習で作った、袋に色セロファンを入れて形作った作品が並んでいました。
「光る魚なんだ。」「これは○○ちゃんのリボン、かわいいね。」そんな話をしていると「先生ぼくが作ったのは、パパ。」と自慢げに自分の作品を見せてくれる児童も集まってきました。「これは、○○ちゃんの。上手だね。ゾウの鼻がついているんだよ。」
自分の作品に自信をもち、友達の作品も称える気持ちが、キラキラしていました。






6月5日「宇宙ステーションでの生活は?」
国語の教科書には、たくさんの本が紹介されています。今日は3年生に、夏休み前のお勧め本を読書活動推進補助教員(白井独自の図書教諭)が紹介しました。今日は『もしも宇宙でくらしたら』山本省三作・村川恭介監修でした。
宇宙で目覚めたら、朝の支度はどうなるでしょうか。食事は全て袋入りです。歯磨きしたら、水はゴックン。学校へは列になって泳ぐように行きます。途中で旗振りの方ならぬ、押してくれる方がいるようになります。学校の先生は手すりを持ちながら教室を回り、子どもたちはシートベルトをしながら学びます。おもしろそう、と言いながらも見えない「地球の引力」のありがたさを感じていました。
今週も3冊ずつ借りていきました。色々な世界に浸ることができそうです。



6月4日「絵本とコラボ給食」
今日の給食に空豆の塩ゆでが出ました。2年生がさやむきをした空豆です。
なかや みわさん 作・絵の『そらまめくんのベッド』を読み聞かせして、空豆は中のふわふわベッドに豆が包まれている、ということが分かり、本物の空豆への期待がふくらみました。また、栄養士から「空豆」という名前の由来も聞きました。空豆は初めは空に向かってさやが大きく育っていくそうです。だから「空豆」なんだと聞き、写真を見ながら「本当だ。」と驚いていました。実ってくると次第にそれが横向きになっていき、下を向き始めたら収穫時期だそうです。
元気に育った新鮮な空豆を、2年生が一生懸命むいてくれました。自分たちでむいた空豆の味は、ひと味違ったようです。
「空に向かって育つなんておもしろかったです。」「外が固くて中がふわふわなのを、初めて知りました。」「いっぱいおかわりしました。」「農家の人が困ったことがあったら、手伝います。」かわいい感想が書かれていました。



6月3日「雨」
運動会が終わり・・・雨です。学校内も少ししっとりしている感じです。その中で、今日だからできる学習を2年生が行っていました。生活科「雨の日のすてきなはっけん」です。
雨の日の素敵を考えていました。「アジサイがきれい。色もいろいろ。」「音がおもしろい」「カタツムリが出てくる」「カエルモ出てくる」「にじが出る」「植物が育つ」・・・。たくさんの意見が黒板に並びました。皆が育てている野菜も、今日は静かに雨に当たっています。
水たまりの素敵は「顔が映ること」「キラキラしていること」だそうです。雨の日もいいかも。



6月1日「勝利をつかめ炎といなずま大決戦」(校長より)
「勝利をつかめ炎といなずま大決戦」のスローガンの下、まさしく「炎のように燃え」、「稲妻のように輝く」運動会が行われ、たくさんの感動が生まれました。プログラムのプロ顔負けの表紙絵もご覧ください。児童が描きました!
応援発表では、各クラスの応援リーダーを中心に、力強い応援が披露されました。徒競走では、一人一人が「昨年の自分を越える」を目標に、真剣な顔でゴール目指す、最後まであきらめない姿が見られました。応援席の自主的な応援も熱が入っていました。団体競技、全校大玉送りは、かわいさあり、力強さあり、こつありの競技で、見ている方も「どっちだ、どっちだ。」と思わず声が出るほど白熱した展開となりました。そして、表現運動。今まで一生懸命練習してきたその姿を見てもらおうと全身で表現する姿に、惜しみない拍手が送られていました。
この時期に行う初めての運動会。様々な「チャレンジ!」が実を結んだ素晴らしい運動会となりました。皆様方の様々なご協力に、心より感謝いたします。


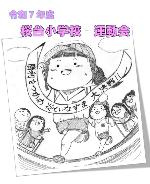












この記事に関するお問い合わせ先
白井市立桜台小学校
〒270-1412 千葉県白井市桜台3-28
電話番号:047-492-7010















更新日:2025年07月04日